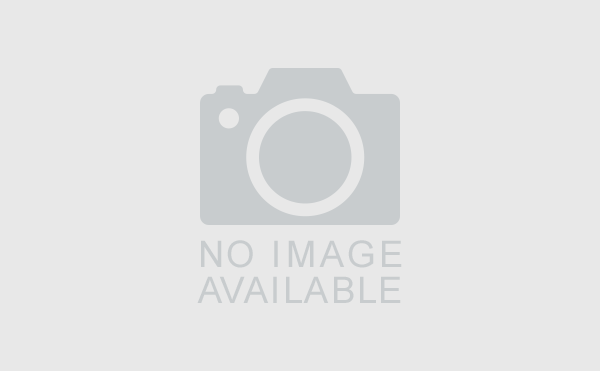【実践コラム】事業展開スピードの「壁」
経営者と金融機関の視点の違いを乗り越える方法について考えます。
事業拡大の局面では、経営者と金融機関の間に大きな認識の隔たりが生じます。特に中小企業や飲食店の多店舗展開では、その傾向が顕著です。たとえば、ある飲食店経営者が銀行融資で2号店を開業し、半年後に好条件の物件を見つけて3号店の融資を相談したところ、「出店ペースが早すぎる」として断られるケースが実際にあります。
経営者にとっては、魅力的な物件との出会いは一期一会であり、スピード感を持って意思決定することが競争優位の源泉です。しかし、金融機関は「まずは2号店の安定化を優先すべき」と慎重な姿勢を崩しません。これは、金融機関が過去の失敗事例から、着実な成長を重視する傾向を強めているためです。回収リスクを避けたい金融機関と、成長機会を逃したくない経営者、両者の間には、事業を進める速度に対する考え方の根本的な違いがあります。
■ 急成長のリスクと金融機関の論理
急速な事業拡大は、資金繰りの悪化や経営管理の複雑化といったリスクを伴います。金融機関は、安定した実績やキャッシュフローを重視し、無理な拡大には融資を渋る傾向があります。これは、貸し倒れリスクを最小化するための合理的な判断です。
一方で、経営者の多くは「2年に1店舗のペースでは、10店舗展開するのに20年もかかってしまう」と、成長スピードの遅さに焦りを感じるものです。しかし実際には、最初の数年で着実に実績を積み上げることで金融機関からの信頼が高まり、その後は融資が受けやすくなります。その結果、出店のペースを後半で大きく加速できるケースが多く見受けられます。例えば、設立から10年で10店舗を展開したある経営者の場合、最初の5年間で3店舗を出店し、次の5年間で一気に7店舗を増やしています。このように、序盤でしっかりと信用を築くことで、後半の成長スピードを上げることが可能になるのです。
では、スピード感を持って成長したい経営者はどうすればよいのでしょうか。ひとつは、銀行以外の資金調達手段、たとえばベンチャーキャピタルやエンジェル投資家など、リスクマネーを供給する機関を活用することです。ただし、株式上場を目指すようなビジネスモデルでなければ、こうした選択肢は限られます。
よって、多くの中小企業にとって現実的なのは、金融機関の論理に合わせた事業計画を立てることです。事業拡大の際は、まずは既存店舗の安定化と実績作りに注力し、金融機関の信頼を積み上げていくことが重要です。加えて、セーフティネット保証や自治体の制度融資など、別枠の資金調達のタイミングを活用し、成長のチャンスを逃さない工夫が求められます。
事業拡大には、経営者の情熱とスピード感が不可欠ですが、金融機関の論理を無視した計画は実現可能性が低くなります。持続的な成長を目指すなら、金融機関の視点を理解し、堅実な実績づくりと計画的な資金調達を組み合わせることが、最終的には最短距離での成長につながります。